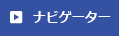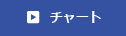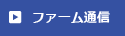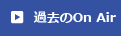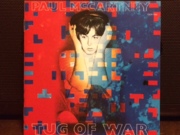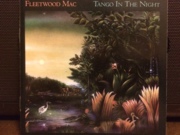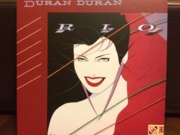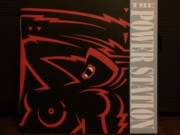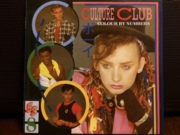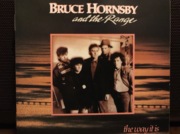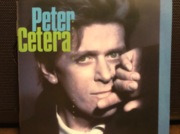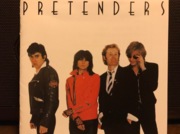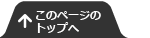第52回 PAUL McCARTNEY『TUG OF WAR』
2018 年 10 月 06 日
●PAUL McCARTNEY:『TUG OF WAR』(1982年)
PaulMcCartney.com |
10/31(水)から来日公演がスタートするポール・マッカートニー。
このところ頻繁にツアーを行い、その都度来日していますね♪
しかも新作リリースを行いながらの
ワールド・ツアーのリピートぶりには感嘆します。
数えきれない名曲を長年に渡って生みだしてきてなお、
まだ「新曲」と「ツアー」に取り組むその音楽欲求は
どこから湧き出てくるんでしょうね??
「ビートルズ世代」では無いyadgeが、
一番好きな彼の楽曲は「カモン・ピープル」という、
アルバム『オフ・ザ・グラウンド』(1993年)に収録されている曲です。
初めて福岡ドームでこのアルバムでのツアー来日公演を見た時、
この曲の最中にステージ横のビジョンに
数々の偉大なる人物の写真が映し出された最後に、
ジョンとポールの二人の写真がそれぞれ両サイドに映し出されて
曲が終わるという劇的な演出がなされたことで
この曲の印象が更に自分の中で大きくなったことを覚えています♪
リアルタイムでポールの音楽を聴いたyadgeが、
初めて「ビートルズらしさ」を感じた思い出深い曲です。
彼の存在を80年代に強く印象付けた曲として、
番組でもアルバムからご紹介した
スティーヴィー・ワンダーとの共演「エボニー・アンド・アイボリー」と、
マイケル・ジャクソンとの共演「セイ・セイ・セイ」(1983年)の
2曲があります。
天才同士、まさに夢の競演であると同時に
「名前負けしない名曲」をちゃんと作り出す神業には言葉がありませんね。
現存するロック・アーティストで
最も成功したアーティスト=ポール・マッカートニー。
その栄誉に甘んずることなくキャリア50年を越えて尚、
エンターテイメントに身も心も捧げている様には改めて胸を打たれます!!
(それはミック・ジャガーも同様に!!)
残るもう一人のビートルズ:リンゴ・スターとともに、
生ける伝説としての輝きを放ち続けて欲しいものです。
●THE FAMOUS ARTIST:LINDSEY BUCKINGHAM
Lindsey Buckingham - Solo Anthology: The Best Of Lindsey Buckingham
先頃、フリートウッド・マックのメンバーに対して
訴えを起こすという残念なニュースが飛び込んできました。
初期リーダーだったピーター・グリーン期の
ブルーズ・バンドから劇的に転身し、
最高峰のポップ・グループとして大成功を収めるに至った経緯には、
このリンジー・バッキンガムの才能貢献が無ければ
成し得ることはありませんでした。
かつての相棒(※元恋人であり、二人同時にフリートウッド・マックに加入)
であったスティーヴィー・ニックスとの再決裂は
恐らく今後、修復するとは考え難いです。。。
彼はシンガー、コンポーザーとして、もちろん「超一級」なのですが、
それにも増して「ギタリスト」としての才覚は
また別次元の輝きを放つものがあります。
番組でもご紹介した「ビッグ・ラヴ」(1987年)が
最もわかりやすいのですが、
元来バンドとしてレコーディングしたこの曲を、
彼は自身のライヴで「アコギ1本」でやり倒します。
そのギター・プレイの衝撃たるや、
名手:マーク・ノップラーに匹敵するため息もののプレイに満ちています♪
Big Love (Live At Saban Theatre In Beverly Hills, CA / 2011) - YouTube
先頃、キャリア総括的なベスト・アルバムのリリースと同時に
アメリカ・ツアーを開始したリンジー・バッキンガム。
片や、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの
ギタリスト:マイク・キャンベルと
クラウデッド・ハウスのニール・フィンという
まさかの人選でリニューアルしてツアーを慣行中のフリートウッド・マック。
Fleetwood Mac - Official Site
完全に分断された現状に、
両者のファンとしては複雑な心境なのであります。。。
第51回 DURAN DURAN『RIO』
2018 年 09 月 29 日
●DURAN DURAN:『RIO』(1982年)
Duran Duran Official Website
間違いなくカルチャー・クラブと並ぶ
「80's洋楽リスナー養成最重要グループ」。
ルックスが良くてバンドとして演奏が出来るグループとしては、
80年代においては彼らが最強だったと思います。
中でもジョン・テイラー(Bass)とニック・ローズ(Key)の二人の
「顔面偏差値」は最高峰でした!!
馬鹿な中学生だったわたしは、大牟田でこの二人が着ていた
パステル・カラーのジャケット&パンツに似た服を無理くり探して、
それに身を包み、チャリンコで街唯一の遊戯場だったボウリング場に行くという
今思えば目も当てられない奇行を繰り返してました。
それくらいこのグループに絶大な「憧れ」を持っていたのです。
やがて「見てくれのカッコよさ」だけではない、
彼ら本来のダークで独特な音楽性と高い楽曲力を知るにつれて
後にU2やボン・ジョヴィ、スティング(ザ・ポリス)などに並ぶ
本当に重要なバンドとしてわたしの中で「絶対化」することになりました。
80年代中期以降、メンバー・チェンジが激しくなり
一時はどうなるんだ?と本気で心配した時期もありましたが、
そのおかげ(?)で後にトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのドラマーとなる
スティーヴ・フェローンを知る事が出来ました。
そのスティーヴ・フェローンがロジャー・テイラーの代役となり、
オリジナル・メンバーが3人となって最初に発表されたアルバム
『ノトーリアス』(1986年)では、
別のグループか?と思い違うほどの演奏と楽曲が披露されました。
Duran Duran - Notorious - YouTube
Duran Duran - Skin Trade (Official Music Video) - YouTube
Duran Duran - Meet El Presidente (Official Music Video) - YouTube
その他にもファンにしか知られていない名曲が彼らには多数、ありますので
この機会に是非こちらもどうぞ♪
Duran Duran - "Do You Believe In Shame" (Official Music Video) - YouTube
Duran Duran - Serious (Official Music Video) - YouTube
Duran Duran - Breath After Breath (Official Music Video) - YouTube
これらの楽曲。
アイドル・バンドだったら、到底創作出来ない仕業なのであります。
「ザ・リフレックス」のたった1曲で、彼らを
「80'sヒット・コンピレーション盤」の中のひとつ、
として片付けようなんてことをするとんでもない輩には、、、
このyadgeが重罪としての罰を与えますから。(笑)
●THE FAMOUS ARTIST:ROBERT PALMER
Robert Palmer - Home
日本では過小評価をされたままお亡くなりになった偉大なるシンガーです。
番組ではデュラン・デュランとの繋がりから、
THE POWER STATION時代の楽曲をご紹介しましたが。
The Power Station - Some Like It Hot - YouTube
彼自身のアルバム群は名盤だらけで
どうしても1曲に絞ることが出来ませんでした。
いずれはアルバム特集アーティストとして、じっくりとお話がしたいです。
中でも思いで深い名盤が『ドント・エクスプレイン』(1990年)。
Don't Explain (Robert Palmer album) - Wikipedia
番組の性質上、
このアルバムは1990年代の作品ですのでご紹介が出来ないので、
この場をお借りして皆様にお見知りおきを頂きたいと思います。
オリジナルとカヴァー曲が入り混じった全18曲というヴォリュームながら、
全ての楽曲が彼のオリジナルであるかのような
錯覚に陥る見事なセンスで構成されており、
長尺さを感じさせない驚異的なクオリティに舌を巻きます♪
その他にも彼には歴代素晴らしいカヴァー&オリジナル曲があります。
お時間が許せばそれらの楽曲の一部もどうぞ。
Robert Palmer - Every Kinda People - YouTube
Robert Palmer - Some Guys Have All The Luck - YouTube
Robert Palmer - I Didn't Mean To Turn You On - YouTube
Robert Palmer - Riptide - YouTube
最後に。
オフィシャルMVが存在しないのでご試聴が頂けませんが、
アルバム『ハニー』(1994年)に収録されている
「ユー・ブロウ・ミー・アウェイ」がわたしにとっての
彼のベスト・トラックです。
Honey (Robert Palmer album) - Wikipedia
※ギタリストはヌーノ・ベッテンコート(エクストリーム)!!!
第50回 CULTURE CLUB『COLOUR BY NUMBERS』
2018 年 09 月 22 日
●CULTURE CLUB:『COLOUR BY NUMBERS』(1983年)
Boy George Official
80年代ブルー・アイド・ソウルと呼ばれた
「白人によるソウル・ミュージックの歌い手」としては。
アメリカ代表はもちろん、ダリル・ホールで。
方やイギリスではジョージ・マイケル、ミック・ハックネル、ポール・ヤング、
そしてボーイ・ジョージという4人衆がそろい踏みでした。
歌が上手いだけでなく、各々が見事にルーツ音楽を上手く取り入れながら
ヒット曲を量産するという離れ業を成し遂げました。
中でもイギリス勢のジョージ・マイケルとボーイ・ジョージは、
カヴァーでは無く「オリジナル曲」でそれを成し遂げた稀有な存在です。
番組内でもお話ししましたが、このカルチャー・クラブの
「カーマは気まぐれ」がわたしを洋楽の世界へと導いてくれた最初の楽曲でした!
Culture Club - Karma Chameleon - YouTube
レンタル・レコード店に貼られていたこの『カラー・バイ・ナンバーズ』の
ポスターに写るボーイ・ジョージを見た時の衝撃と。
実際にアルバムを聴いた時の歌の上手さの衝撃というダブル・ショック。
次回特集するデュラン・デュランも同様に、
ある種「アイドル的な存在以上」に認められない風潮がありますが、
あらゆる観点からみても、この2つのグループの実力と功績は
否定のしようがありません。
70年代のアイドル・グループであるベイ・シティ・ローラーズには無い、
「音楽的深度」がこの2グループには明らかに内包されています。
デュラン・デュランについては次の項で詳しく書きますが、
とにかくボーイ・ジョージというアーティストの
総合的かつ唯一無二な魅力は80年代洋楽シーンにおいて、
マドンナ、マイケル・ジャクソン並みに強力なインパクトを放ちました。
再びアルバム・リリースとそのツアーで音楽シーンに返り咲くその様を、
yadgeはとくと見届けたいと思います♪
願わくば、来日公演のライヴを見たいです!!!
●THE FAMOUS ARTIST:MICHAEL FRANKS
Singer/Songwriter Michael Franks
プロデュサーにトミー・リピューマ。エンジニアにアル・シュミット。
そしてレコーディング・メンバーには
ジャズ・フュージョン界のトップ・プレイヤーが大挙参加。
そんな面々で作られたアルバムが悪いはずがありません。
1977年リリースの『スリーピング・ジプシー』。
いまでも少し背伸びして大人な雰囲気を感じたいときに手にする作品です。
それでいて果てしなく心地よく、幸せな気分を味わえる
とても貴重な作品でもあります。
チャート上での実績以上に、このアルバムが与えた影響力の大きさは
計り知れないと思います。
1977年当時のかまやつひろしさんが、
ライナーノーツに寄稿されていらっしゃいます。
そこで彼が無条件に絶賛していることを知った時は、驚きでした。
番組でご紹介したアルバム収録曲「淑女の想い」(邦題)を
初めて耳にしたのは、今井美樹さんのよるカヴァーでした。
彼女のカヴァー・アルバム『フィエスタ』(1988年)に収録されています。
「fiesta」|DISCOGRAPHY|今井美樹オフィシャルサイト[imai-miki.net]
ご存じなかった方は是非、こちらのヴァージョンもお聴きになってみて下さい♪
現在もマイ・ペースで着々と
独自のキャリアを重ねているマイケル・フランクス。
何故かその姿が、ボズ・スキャッグスと重なるものを感じるのは
わたしだけでしょうか?
第49回 BRUCE HORNSBY and the Range『THE WAY IT IS』
2018 年 09 月 15 日
●BRUCE HORNSBY and the Range:『THE WAY IT IS』(1986年)
Bruce Hornsby
アメリカを代表するピアノ・プレイヤーとして
yadgeが真っ先に名を挙げたいのが、このブルース・ホーンズビーです。
もちろん「シンガーソングライター」として歌も素晴らしいのですが、
何といっても彼が奏でるピアノの「音色」は唯一無二。
番組内でも申し上げましたが、強烈な「個性」となっています。
No.1シングル曲「ザ・ウェイ・イット・イズ」はもちろん。
The Way It Is - YouTube
キャリア最高楽曲だと信じて止まない大名曲「マンドリン・レイン」も、
たまりません!!
Bruce Hornsby & The Noisemakers - "Mandolin Rain" (The Way It Is - 2016 Live Compilation) - YouTube
加えて、ドン・ヘンリーと共作・共演した
「ジ・エンド・オブ・ジ・イノセンス」(1989年)でも
その素晴らしいピアノ・プレイが堪能できます。
ポピュラー・ヒットとは縁遠い音楽活動を経て久しいですが、
現在もアメリカン・ルーツ・ミュージックの担い手として
アルバム作品やツアーを通じて「音楽に対する尊敬の念」をもちながら
誠実に音楽活動を継続中です♪
日本ではなかなか紹介される機会が少ないミュージシャンではありますが、
yadgeは生涯をかけて彼の存在を
少しでも多くの音楽ファンの方々に知らしめていけたらと思っています。
●THE FAMOUS ARTIST:PETER CETERA
Peter Cetera
「Voice of CHICAGO」
彼のキャリアを語る際に、このキャッチは外すことが出来ません。
60年代~70年代に「ブラス・ロックの旗手」として
メッセージ色の強い歌詞と共にその偉大なる存在感を
音楽史に刻み続けてきたシカゴを。
80年代に、よりポップ・ミュージックに寄せた音楽性で
「ヒット・シングル」を連発するグループに様替えをさせて
あらたな時代を生き抜くことに成功しました。
その大きな要因となったのが、他でもなく
このピーター・セテラのダイアモンド・ヴォイスと、
プロデューサーで共作者でもあるデヴィッド・フォスターの存在でした。
問答無用の80'sヒット・バラードを2連発でどうぞ!!
Chicago - Hard To Say I'm Sorry/Get Away (Official Audio) - YouTube
Chicago - You're The Inspiration (Official Music Video) - YouTube
このハイトーン・ヴォイス、
同時代の男性人気シンガーの中でも屈指のハイ・キーだったと思います。
(肩を並べるのはスティーヴィー・ワンダーかスティーヴ・ペリーくらい?)
その魅力を楽曲に十二分に反映させたデヴィッド・フォスターの手腕たるや、
やはり特筆すべき偉業だと思います。
グループからソロに転向後も全米No.1ヒットを出し続けた成功例は、
ザ・ビートルズのあの2人、マイケル・ジャクソン、ライオネル・リッチー、
フィル・コリンズなど、さほど多数ではない偉業なわけでして。
そんなことを改めて思い返すいい機会になりました♪
第48回 ELTON JOHN『GOODBYE YELLOW BRICK ROAD』
2018 年 09 月 08 日
●ELTON JOHN:『GOODBYE YELLOW BRICK ROAD』(1972年)
Elton John
アメリカのビリー・ジョエル、イギリスのエルトン・ジョン。
「ピアノマン」としてこの2人が
ポピュラー・ミュージック史に残した功績の偉大さは計り知れないものがあります。
とりわけエルトン・ジョンのヒット曲は70年代~現在に至るまで
断続的に生まれ続けており、ポピュラー音楽史において
他を寄せ付けない圧倒的な音楽家としての才能を発揮し続けています。
個人的な想い出話をひとつ。
大学生時代に桑田佳祐さんのラジオ番組『サウンド・ストリート』で一度、
ハガキを読まれたことがあります。
内容は「生涯のベスト3」の曲を書いたもので、
その時に1位にした曲がエルトン・ジョンの
「サッド・ソングス(セイ・ソー・マッチ)」でした。
Elton John - Sad Songs (Say So Much) - YouTube
桑田さんの番組で自分のリクエストとしてエルトン・ジョンの曲を採用して頂いた事で、
その時から私の中でのエルトン・ジョンの存在が
絶対化したのは言うまでもありません。
90年代に入ってリリースされたアルバム
『The One』(1992年)からのタイトル曲も、また素晴らしく。
Elton John - The One - YouTube
※ピノ・パラディーノによる素晴らしいベース・プレイも必聴♪
遂にキャリアを締め括るかのようなラスト・ツアーを開始したエルトン・ジョン。
来日公演、更には福岡公演が実現することを切に願ってます!!
●THE FAMOUS ARTIST:CHRISSIE HYNDE(THE PRETENDERS)
PRETENDERS
80年代以降に登場した女性ロッカーで一番カッコよく、
そのスタイルを貫き通している唯一とも言える存在。
イギリス・ロック界最大の存在のひとつである「ザ・キンクス」の
レイ・デイヴィスとの結婚歴も、並みの人生からはかけ離れています。
しかも「憧れの存在だった人物」との結婚ですから。
更にシンプル・マインズのジム・カーとの再婚劇も二度目の驚きでした。
その2番目の旦那さんだった人のバンドと時を経て今、
ジョイント・ツアーをやるって、お互いどんな感覚なんでしょうかね??
まぁとにかく。
この方の「佇まい」は絵に描いたようなカッコよさで、
テレキャスターを手にマイクスタンドの前に立つその姿だけで
しびれるものがあります!
加えてクールな歌声も相まって、「ロック姐御」的なオーラが
瞬時に見る者の心をワシ掴みに♪
オフィシャル・チャンネルが無いのでここで映像をご紹介出来ないのが残念ですが、
機会があれば是非映像でも彼女のカッコよさを実感して下さい。