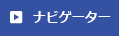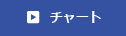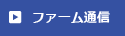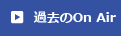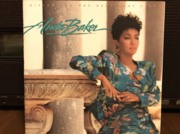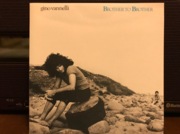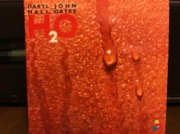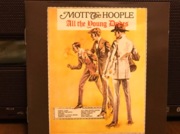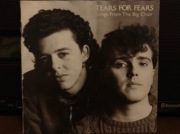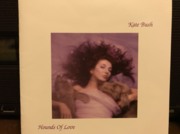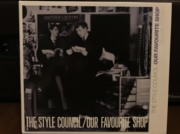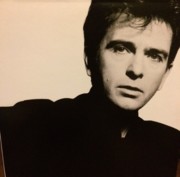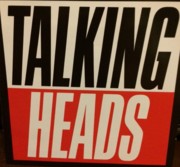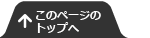第37回 ANITA BAKER『GIVING YOU THE BEST THAT I GOT』
2018 年 06 月 16 日
●ANITA BAKER:『GIVING YOU THE BEST THAT I GOT』(1988年)
Anita Baker(@IAMANITABAKER)さん | Twitter
オフィシャル・サイトが見つからなかったので
ツイッターが最新情報源かと思われます。
引退宣言の後、キャリア最期となる
アメリカ公演を行っているアニタ・ベイカー。
1980年代の終盤。
混沌としていた音楽シーンにR&B/SOUL MUSICを
絶妙に自分自身の「色」をブレンドして、
高校生の若造にも「おしゃれで良い音楽だなぁ~♪」と
知らしめてくれた女性アーティストでした。
ブレイク作となったアルバム『ラプチュア』(1986年)で
「クワイエット・ストーム」なる新たに称された音楽シーンの中心的存在となり、
その存在感は他を寄せ付けない唯一無二のものでした。
加えて彼女が凄いところは、ただ「歌が上手いシンガー」だけでなく、
コンポーザー、プロデューサーとしての才能も備えていたところです。
流行りの打ち込みサウンドによる安っぽく消費されがちだった
当時のブラック・ミュージックとは一線を画し、
このアルバム『GIVING~』でのサウンド・プロダクションは、
オマー・ハキム(Dr)、ネイザン・イースト(Bass)、
ポール・ジャクソン・Jr.(Gt)などの
超一流ミュージシャンを起用しての「鉄壁の音」が施されていました。
そのあたりの「コンテンポラリー・シンガー」としての自意識の高さと
それに見合う優れた楽曲を兼ね備えていたことが
アニタ・ベイカーという稀有な存在感の演出に大きく関与していたのでは?
と思います。
今後、新作を聴くことは出来ないかもしれませんが、
この素晴らしいアーティストが残してきたアルバム群を
機会があれば是非、お聴きになってみて下さい♪
●THE FAMOUS ARTIST:GINO VANNELLI
Gino Vannelli Official Website | GinoV.com
普段はラジオでも紹介されることが少ない
「知る人ぞ知る」天才アーティストかもしれません。
かくいうyadgeも、
番組でご紹介した「I Just Wanna Stop」が収録されているアルバム
『ブラザー・トゥ・ブラザー』(1978年)で後追いで初めて存在を知り、
その後アルバム数枚を手に入れましたが
キャリアのすべてを網羅するまでには至っていません。
なかなか情報が入ってこないアーティストだったので、
今のようにインターネットを駆使出来なかった時代では
いわゆる「売れているアーティスト」のように
彼の新作や活動情報が常時耳に入ることはありませんでした。
アルバム『ブラザー~』のライナーノーツを読むと、
引き合いにスティーリー・ダンの名前が書かれていて
「A.O.R.アーティスト」かのような括りで語られていますが、
実際の音楽はもっとロックでプログレッシヴなものでした。
ジノ・ヴァネリ本人も含めて、
レコーディング・メンバーの恐ろしくハイ・クオリティな演奏力が
聴くものを圧倒する彼の最高傑作と言われているアルバムです♪
「言われている」と、断言できないのは
先にも書いた通りまだ彼の全作品を聴いたことが無いので。。。(笑)
yadge自身、まだまだ彼の音楽の探求の旅は続くのであります。
第36回 DARYL HALL&JOHN OATES『H2O』
2018 年 06 月 09 日
●DARYL HALL&JOHN OATES:『H2O』(1982年)
Official Site | Daryl Hall and John Oates :: Daryl Hall and John Oates News, Tour Dates, Discography, Music, Videos, Photos and Fan Club
「ブルー・アイド・ソウル」
(=青い瞳のソウル、つまり白人が歌うソウル・ミュージックのこと)。
この言葉が最も相応しかった80'sアーティストの一組が、
ホール&オーツでした。
彼らが「アメリカ代表」だとすれば、「イギリス代表」は
シンプリー・レッドのミック・ハックネルでしょうか。
2人の音楽基礎である「ソウル・ミュージック」を
巧みに取り入れて「独自のポップ・ミュージック」として昇華し
数多くの大ヒット・シングルを作り続けたその功績は計り知れません。
その音楽センスもさることながら、
やはり特筆すべきはダリル・ホールの「歌の上手さ」!!
まぁとにかく彼のヴォーカリストとしての表現力は、
同時代の歌い手の中ではダントツです。
♪アルバム特集内でもご紹介した「One On One」などは
分かりやすい実例です。
Daryl Hall & John Oates - One On One - YouTube
中学~高校生時代にポピュラー洋楽に目覚めて
その世界の素晴らしさに深入りを始めたyadgeにとって、
ホール&オーツの存在は、デュラン・デュラン、
カルチャー・クラブと並ぶ最重要アーティストの1組でした。
彼らに出会っていなければ
(、、、というか洋楽好きであれば
間違いなく出会ってしまう存在ですが!)、
今の自分を形成する音楽素養を得ることは無かったと思います。
そして60~70年代ソウル・ミュージックの
素晴らしさを教えてくれた
「アメリカ音楽の先生」的な存在でもありました。
彼らが80年代に遺してきたヒット曲群も、
きっと60~70年代のヒット音楽と同様に
「時代を代表するヒット曲」として真っ先に例に挙げられ、
語り継がれていくことは間違いないと思います。
♪ライヴで聴くと一番シビれるのが、この「Wait For me」。
Daryl Hall & John Oates - Wait For Me - YouTube
●THE FAMOUS ARTIST:IAN HUNTER(MOTT THE HOOPLE)
わたくしyadgeは、故デヴィッド・ボウイを知らなければ、
彼の存在を知ることはありませんでした。
イアン・ハンター(モット・ザ・フープル)と
デヴィッド・ボウイの関係は
「All The Young Dudes」(1972年。邦題:すべての若き野郎ども)
という1曲ですべてが語りつくせるほどの強力な楽曲だと思います。
♪映像はコチラ。
MOTTTHEHOOPLEVEVO - YouTube
グループの解散危機を
デヴィッド・ボウイ作のこの1曲で乗り切るどころか、
ロック史に残る名曲として語り継がれる存在となったのですから、
いかにでデヴィッド・ボウイの功績が大きかったか。。。
なんだかイアン・ハンターじゃなく
デヴィッド・ボウイのことばかりを
ほめちぎる文章となってしまいましたね。(笑)
イアン・ハンターはソロ・アーティストとしても
素晴らしいアルバムをリリースしています。
中でも1976年リリースの『All American Alien Boy』は、
ジャコ・パストリアス(Bass)、デヴィッド・サンボーン(Sax)、
コーネル・デュプリー(Gt)などの
超豪華ゲスト・ミュージシャンが参加している名盤です!!
モット・ザ・フープルしかご存知ない方も、
機会があれば是非イアン・ハンターの作品もお聴きになってみて下さい♪
News Headlines | Mott The Hoople
第35回 TEARS FOR FEARS『SONGS FROM THE BIG CHAIR』
2018 年 06 月 02 日
※お詫び。
番組中で3rdアルバム『THE SEEDS OF LOVE』の発売年を
誤って「1983年」と言っておりました。
こちら正しくは「1989年」でございます。
この場をお借りしてお詫びして訂正とさせて頂きます。
申し訳ございませんでした。
●TEARS FOR FEARS:『SONGS FROM THE BIG CHAIR』(1985年)
ローランド・オーザバル(Vo&Gt)とカート・スミス(Vo&Bass)。
Tears For Fears
絶妙なバランスで緊張感を保ちながら、
その音楽的才能を余すことなく80年代に開花させた2人組です。
番組でご紹介した2ndアルバムももちろん素晴らしいですが、
yadge的には彼らの最高傑作は次作である
『THE SEEDS OF LOVE』(1989年)です。
更に言えば、彼らの最高傑作というに留まらず
「80年代UK全アルバム」というくくりでも
「最高傑作」と呼ぶに相応しい奇跡の1枚だと。
ローランド・オーザバルのソングライターとしての資質と、
それを具現化・音像化する素晴らしいゲスト・ミュージシャンの演奏♪
そのどれもが他に類を見ない異次元のクオリティで
アルバム1枚に凝縮されています。
もうこれ以上の言葉はありません。。。
♪そのアルバム冒頭を飾るベスト・トラック
「Woman In Chains」はコチラからどうぞ。
※レコーディング・ドラマーはフィル・コリンズ!!
Tears For Fears - Woman In Chains - YouTube
今年中に新作がリリースされるとのニュースが発表されていますが、
延期することなく無事にリリースされることを心から願っています。
きっとまた素晴らしい作品であることを確信しています!!
♪最新ベスト・アルバムに収録された新曲はコチラ。
TearsForFearsVEVO - YouTube
♪ひとりになったローランド時代の超~名曲「Goodnight Song」はコチラ。
Tears For Fears - Goodnight Song - YouTube
第34回 KATE BUSH『HOUNDS OF LOVE』
2018 年 05 月 26 日
●KATE BUSH:『HOUNDS OF LOVE』(1985年)
デビュー時にピンク・フロイドのデヴィッド・ギルモアが
プロデュースを買って出たエピソードから
早くもアーティストとしての「格の違い」を見せつけていた規格外の才女。
他に類を見ない独自の音楽性はキャリアを通じて貫かれています。
番組内でもお話した通り、彼女はライヴ・ツアーをほとんど行っていないので
いまひとつ音楽活動の実体がつかめない
「ミステリアスなアーティスト」でもあります。
日本でのポピュラリティが同時代の女性アーティストである
マドンナ、シンディ・ローパー、SADEや
アニー・レノックス(ユーリズミックス)に比べると圧倒的に低いのも、
情報量が少なすぎるのが一因かもしれませんね。
だからこそ、今初めて彼女のことを知った方々にも是非、
彼女の音楽にこれから触れて頂けたらと願っています。
本作『HOUNDS OF LOVE/邦題:愛のかたち』は、
彼女のアルバム群の中でもおススメの作品です♪
発売当時15歳で耳にしていたわたしが、48歳になった今、
改めて聴いてもまた”深み”が増していく不思議なアルバムです。
ということは「一生かけて」聴いても、
永遠と感動を与えれくれるアルバムということです。
みなさまの長く愛聴できるアルバムの1枚になりますように。。。
Homepage | Kate Bush
まずは、改めてこの曲からどうぞ♪↓
こんなカッコいい曲、そうそうありません。
Kate Bush - Running Up That Hill - Official Music Video - YouTube
●THE FAMOUS ARTIST:PAUL WELLER(THE STYLE COUNCIL)
ザ・ジャム~ザ・スタイル・カウンシル~ソロと、
音楽性を多様に変化させながらも絶妙なバランスで
音楽キャリアを重ねている様は、STINGと重なるものを感じます。
ルックス良し、才能もありあり。
この2人を称するに最もシンプルな言葉ですね。
個人的にはPUNKが苦手なので、やはりザ・ジャム解散後、
80年代中期~後期:ザ・スタイル・カウンシル時代の彼の音楽が
一番肌に合っています。
当時は「おしゃれな音楽」のひとまとめで、
SADE、スウィングアウト・シスターと同列で聴いていました。
JAZZやSOUL MUSIOの要素が多分に含まれていた
スタイル・カウンシルの音楽は、
ヘビメタ/ハードロックにドップリ漬かりつつもあった
中学~高校生当時のyadgeの音楽指向の中での
「清涼剤」的な存在だったと思います。
「うるさい音楽で耳が疲れたら聴く」、的な。
しかもそれを聴いていること自体が「かっこいいかな」、と!(笑)
グループ名(※カウンシル=評議)も絶妙でした!
天才:ポール・ウェラーのイメージ戦略にまんまとハマったわけです。
60歳となった今でも、ソロ・アーティストとしての
「理想形」を邁進するカッコよさは、不変です♪
Paul Weller
番組でご紹介した「シャウト・トゥ・ザ・トップ」はこちら↓
The Style Council - Shout To The Top - YouTube
日本の音楽ユニット:paris match が、
ザ・スタイル・カウンシルの楽曲名から付けられたことも有名です♪
paris match|Victor Entertainment
第33回 PETER GABRIEL『So』
2018 年 05 月 19 日
●PETER GABRIEL:『So』(1986年)
前週で特集したポール・サイモン『GRACELAND』と共に
「1986年」を象徴する最重要作品です。
番組内でのキーワードにしていた「リズム」というワード、
この2作品に極まれり!ってな感じです。
通常、グループやユニットからソロに転向したアーティストが
かつてのキャリアに勝る作品を成しえるということは至難の業です。
例えば、ザ・ローリング・ストーンズのミック・ジャガー、
クイーンのフレディ・マーキュリーはソロとしての成功は
グループより明らかに劣ります。
元々の「音楽IQ」が、ピーター・ゲイブリエル、
ポール・サイモンやスティングは他アーティストとは別次元なのでしょうね。
本作『So』で特筆すべきは、その内容ももちろんですが
「音の良さ」も忘れることが出来ません。
とりわけアルバム冒頭を飾る「Red Rain」の
イントロのハイハット・シンバルの刻み
(byスチュワート・コープランド!from The Police)から、
ギターとリズムが重なってきて曲想に入る部分の音像の広がりは
本作のサウンド・プロダクションのハイライトのひとつです♪
80年代の名盤音像としては、ロキシー・ミュージックの最高傑作
『アヴァロン』の冒頭を飾る「More Than This」のイントロに匹敵します。
音像が究極に素晴らしいのは、レコーディング・スタッフの技術に加えて
当の演奏家達があまりにも素晴らしいからです。
後にスティングが2ndソロ・アルバム
『...Nothing Like The Sun』で起用するドラマーのマヌ・カッチェを筆頭に、
もう一人の優れたドラマーであるジェリー・マロッタ。
リズム・コンビを支えるベーシストのトニー・レヴィン
(現在はキング・クリムゾンのメンバー!)。
そして空間的音像の要とも言える長年のレギュラー・メンバーである
デヴィッド・ローズによるギター。
ピーター・ゲイブリエルが創造する音楽を
一言一句違うことなく「再現」出来る演奏家としての技量たるや、
まさに「超理想的」な面々です。
「高質でありかつポピュラリティを持ち得る数少ないアルバム」の例が、
本作『So』だと言えます。
同じお金を払って音楽を聴くのだとすれば、
正に本作のようなクオリティの作品を「基準」に置いておけば、
選ぶ音楽を間違えることは無いのですが。
私達愚かな音楽ファンは、常に多くの「そうでは無いアルバム」も
たくさん耳にしてバランスをとっているんですよね。。。
つまり、何も考えずに聴ける能天気なポップ・ソングは絶対に必要だ!という事です。
だって毎週この番組がピーター・ゲイブリエル、スティング、
ポール・サイモンの特集だったら疲れませんか!?
少なくともわたしは疲れます。(笑)
、、、とそんなどうでもいいことを理屈っぽく語りたくなるくらい、
このアルバムは明らかに「別格である」という事です。
News - PeterGabriel.com
「Red Rain」はこちら↓
Peter Gabriel - Red Rain - YouTube
●THE FAMOUS ARTIST:DAVID BYRNE(TALKING HEADS)
先のピーター・ゲイブリエル並みに音楽IQが高すぎる(?)アーティスト、
デヴィッド・バーン。
「リズム」というキーワードへの答えは
トーキング・ヘッズ時代の最高傑作とされる
『REMAIN IN LIGHT』(1980年)で既に実証済み。
このアーティストもいはゆる欧米音楽文化には無い「リズム」を
作品の中で顕著に体現している数少ないアーティストのひとりです。
ときにへなへなとしたクセのあるヴォーカルが聴き手を惑わすこともありますが、
逆にその個性的な歌声や歌い方が尚いっそう、
彼の音楽性を唯一無二のものとしている大きな要因になっています。
トーキング・ヘッズ時代~ソロ作品を含めて、
まるでカメレオンのように作風を変えてくるその様に
時についていけないこともありますが。
その難解さは長い時間をかけて解読していく楽しみがある長編推理小説のようなもの。
きっと一度ハマれば止められない「中毒性」が、
彼の音楽作品にはあるのでしょうね♪
Talking Heads (official) - ホーム
David Byrne
最も分かりやすい彼のPOP TUNE:「Road To Nowhere」はこちら↓
Talking Heads - Road to Nowhere (Official Video) - YouTube
そして「80s音楽映画の最高傑作」との評価を受けている
『STOP MAIKING SENSE』(1984年)も
機会があれば是非、ご覧になって下さい♪↓(予告編)
ストップ・メイキング・センス(字幕版) - YouTube